Background and Purpose
設立の背景と目的
大規模言語モデル(LLM)を国内で稼働させる必要性(国益・技術戦略)
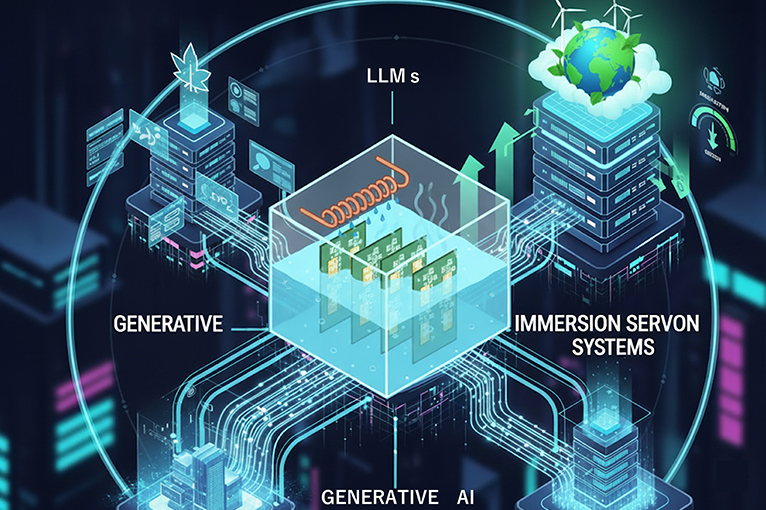
近年、生成AIや大規模言語モデル(LLM)は社会や産業のあらゆる分野に浸透しつつあり、その活用が競争力の源泉となっています。特に自然言語処理、医療・製薬分野の解析、製造業における設計支援や最適化など、幅広い領域でイノベーションを加速させる存在となっています。
しかし現状では、多くの先進的なLLM基盤は海外の巨大事業者が保有・運営しており、日本国内の利用はクラウドを通じて依存せざるを得ない状況です。このことは、①機密性の高いデータを国外の基盤に委ねるリスク、②利用コストの国外流出、③国内研究者・企業が基盤技術に直接アクセスできない不利、といった問題を招きかねません。
国内においてLLMを稼働させる環境を整備することは、国益の観点から極めて重要です。自前の情報インフラを確保することで、データ主権を守り、国内企業や研究者が安心してAIを活用できる基盤を築くことができます。また、エネルギー効率に優れた液浸冷却技術を組み合わせることで、膨大な演算処理を伴うLLMの運用を持続可能な形で実現でき、日本発の技術力を世界に示す戦略的意義もあります。
オールジャパンでの取り組みの必要性(産学官連携・国際競争力)
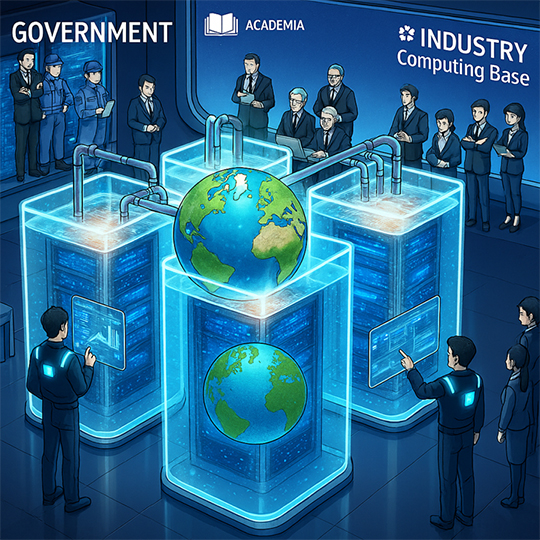
液浸冷却をはじめとする次世代冷却技術は、単一企業や研究機関の努力だけで確立できるものではありません。高性能半導体、冷却液、筐体設計、インフラ構築、運用システムなど、多様な専門領域が複雑に関わり合うため、産業界・学術界・行政が連携し、一体となった取り組みを進めることが不可欠です。
特に海外では、大規模なコンソーシアムや標準化団体が強力に推進力を発揮し、国際市場における主導権を確立しつつあります。日本がこの潮流に後れを取れば、技術的優位性を失うだけでなく、産業競争力そのものが大きく損なわれる可能性があります。
そのため、日本発の液浸冷却技術をグローバルに展開するには、オールジャパン体制での連携が不可欠です。産学官の枠を超えた共創の場を構築し、研究成果を標準化・実装につなげることで、日本の技術力を国際社会に発信し、未来のエネルギー社会に貢献することが求められています。
消費電力の増加による所得移転(課題提示)
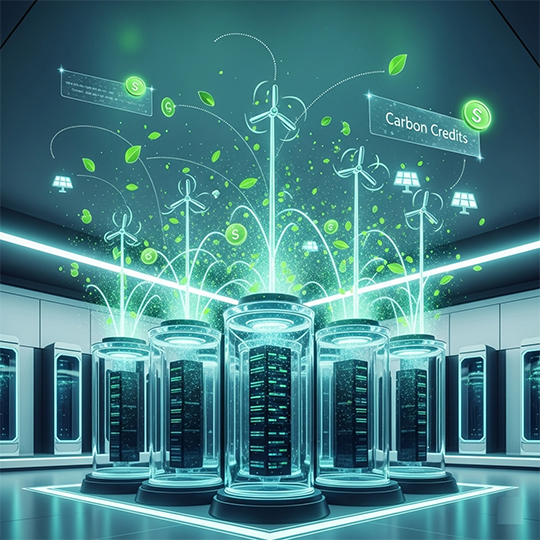
世界的なデジタル化の進展に伴い、電力需要は年々増加しています。特にクラウドサービスや生成AI、大規模言語モデル(LLM)の普及により、データセンターが消費する電力量は急激に拡大しており、今後も加速度的な増加が見込まれます。
このような状況では、電力価格の高騰が産業や国民生活に直接的な負担として跳ね返ります。電力の多くを海外からの燃料輸入に依存する国では、エネルギーコストの増大がそのまま国外への所得流出につながり、国内の経済基盤を弱体化させるリスクがあります。つまり「電力を大量に消費する=エネルギー調達国への富の移転」を意味しており、持続可能な成長にとって大きな課題となっています。
したがって、社会全体の電力消費を抑制しつつ、安定した情報基盤を維持するための省エネルギー技術の導入が急務です。その解決策のひとつが、従来の空冷方式に比べて効率的に機器を冷却できる「液浸冷却技術」であり、冷却に伴う電力投入を大幅に削減する可能性を秘めています。
Greeting
代表挨拶

代表理事
結城 和久(山口東京理科大学工学部機械工学科 教授)
当法人は、グリーントランスフォーメーション(いわゆる「GX」)の取り組みに基づき、半導体素子の冷却液浸漬(液浸)冷却技術を普及させ、標準化に向けた運用指針を制定してまいります。
現在、世界は深刻なエネルギー危機と環境問題に直面しています。特に急成長を見せる高度情報化社会によりAIデータセンターの電力需要は2030年までに4倍になると予想され、その値は2024年水準から倍増、日本の総電力消費量を超える勢いです。今後、豊かな高度情報化社会とカーボンニュートラルを両立するには、安価で安定した電力供給源の確保はもとより、データセンターの省エネ化が最重要課題となります。
このような背景のもと、冷却に伴う電力投入を大幅に削減可能で、かつ高い冷却性能を得ることが可能な液浸冷却技術が注目を集めています。すでにサーバ分野では、液浸冷却システムの商用化も一部開始され、今後、日本オリジナルの冷却技術としてグローバル展開を更に強化、産学官の枠組みを超えてイノベーションを創出し、社会実装を加速するためのフレームワークの構築が急務です。そこで、ステイクホルダーとの共創の場として「一般社団法人日本液浸コンソーシアム」を設立しました。
是非、このコンソーシアムの場をご活用いただき、高度情報化社会を担う新しい冷却技術や関連技術を武器に、液浸冷却システムの標準化に向けた運用指針を世界に先駆けて策定できればと強く期待しています。
略歴
1998年 九州大学大学院 総合理工学研究科 博士後期課程を修了後、東北大学大学院工学研究科にて11年勤務。
2009年から現在まで山口東京理科大学工学部に在職。主として高発熱密度電子機器の冷却研究に従事。
特に車載用インバータやデータセンタの冷却、電子機器の実装技術に関わる熱抵抗軽減技術などの熱問題について研究。 現在、
- 日本伝熱学会中国四国支部 支部長
- 中四国熱科学工学研究会 理事長
- 日本機械学会 分科会RC301 委員
- 日本機械学会熱工学コンファレンス 代表オーガナイザー
- PCTFE Vice-President
Outline
組織概要
| 会社名 | 一般社団法人 日本液浸コンソーシアム |
|---|---|
| 所在地 | 〒756-0884 山口県山陽小野田市大学通1丁目1−1 |
| TEL | 080-5163-9396 |
| 設立 | 2025年6月2日 |
| info@immersion-cooling.jp | |
| 事業内容 | 当法人は、グリーントランスフォーメーション(いわゆる「GX」)の取り組みに基づき、半導体素子の冷却液浸漬(液浸)冷却技術を普及させ、標準化に向けた運用指針を制定することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。 1.研究会等の共創・交流・教育に必要な事業 2.液浸運用ルール制定と認可制定のための受託評価事業 3.標準化に向けた指針制定事業 4.その他、当法人の目的を達するために必要な事業 |
Board Members
役員一覧
代表理事
結城 和久(山口東京理科大学 教授)
理事
- 犀川 眞一(篠原電機株式会社 専務取締役)
- 井手 拓哉(株式会社ロータス・サーマル・ソリューション 代表取締役社長)
- 松井 覚(篠原電機株式会社 部長)
- 野村 光(東北大学 国際放射光イノベーション・スマート研究センター 准教授)
監事
- 竹内 茂隆(梅ヶ枝中央会計株式会社 公認会計士)
- 外山 弘(外山法律事務所 弁護士)

